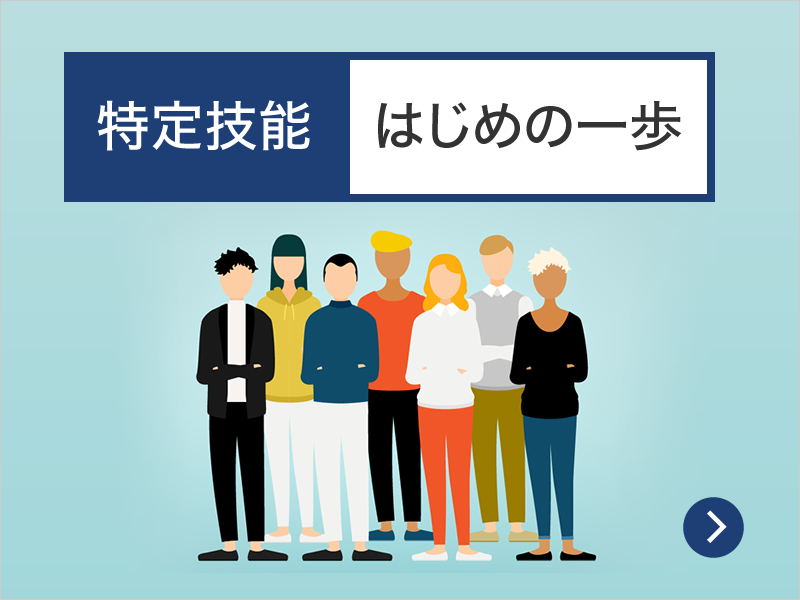2027年に育成就労制度の開始が予定される中、登録支援機関の必要性はますます高まっています。
本日は、個人事業主が登録支援機関になる場合の要件などについて、行政書士の小澤先生にお話しを伺います。

小澤先生、本日はよろしくお願いいたします。
小澤 よろしくお願いします。
さっそくですが、個人事業主でも登録支援機関になれるのでしょうか?
小澤 はい。個人事業主でも、要件を満たしていれば問題なく登録支援機関になれます。
先生は登録支援機関登録申請もおこなっていると伺いましたが、今までに個人事業主の申請を扱った事例はございますか?
小澤 何度もあります。
それで、申請結果はいかがだったでしょうか。
小澤 当事務所で扱った案件については、全て登録支援機関として登録されました。
「許可」になったということですか?
小澤 そうです。登録支援機関登録申請の場合、許可申請ではなく登録申請なので、「登録」とうい言い方をしますが、わかりやすく言えば「許可」ということです。
心強いです。許可されるために必要なポイントはありますか?
小澤 はい。登録支援機関として登録されるために必要なポイントはいくつかあります。
個人事業主が登録支援機関登録申請する際のポイント
具体的にはどのような点がポイントになるのでしょうか。
小澤 入管法第19条の26に、登録支援機関の登録拒否事由が定められています。この登録拒否事由に該当すると、登録支援機関にはなれません。登録拒否事由は全部で14項目あります。登録拒否事由には、法令に違反して罰金刑に処せられたことの有無や、執行後5年を経過しているかなどを問う項目が多いのですが、ポイントとなるのは14番目の項目です。
14番目はどのような内容でしょうか。
小澤 入管法第19条の26第1項第14号には次のように記載されています。
・14支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
そして「必要な体制が整備されていない者」として、法務省令である入管法施行規則では8項目を定めていますが、ポイントとなるのは次の3項目目です。
入管法施行規則第19条の21第3号
3 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が,過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が,過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか,登録支援機関になろうとする者が,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
難しいですね。「次のいずれにも該当しない者」ということは、イからニに「該当していない」なら、登録支援機関の要件を満たすということでしょうか。
小澤 逆です。登録支援機関として登録されるためには、イからニのどれかに「該当している」必要があります。
??? どういうことでしょうか?
小澤 こういうことです。
入管法第19条の26で登録拒否事由を定めています。つまり、入管法第19条の26に書いてある項目に該当すると、登録支援機関になれない。
↓
入管法第19条の26第1項第14号「必要な体制が整備されていない者」として法務省令で定めるものは登録支援機関になれない。
↓
法務省令「次のいずれにも該当しないもの」は「必要な体制が整備されていない者」とする。
↓
言い換えると
↓
「次のいずれかに該当するもの」は「必要な体制が整備されている者」とする。
なので、登録支援機関として登録されるためには、イからニのどれかに「該当している」必要があるんです。
ここまでは大丈夫ですか?
なんとか大丈夫です。
小澤 元の条文がわかりにくい表現なので、正確に読み込めなくても大丈夫です。ここではひとまず、イからニのどれかに該当している必要があることだけ押さえておきましょう。
先に進みましょう。登録支援機関になるには、入管法施行規則第19条の21第3号のイからニのどれかに該当していなければならない。では、個人事業主はイからニのどれに該当するのか。
そこです。そこを教えて頂けますか?
要件イ 受入れ管理実績要件
小澤 個人事業主の場合は、イロハのどれかで申請するケースが多いです。
まずイの要件を見てみましょう。入管法施行規則第19条の21第3号に書いてある文言を要約すると次のようになります。
「過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなった実績があること」
「就労系の中長期在留者」というのは、入管法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格のことです。
| 別表第1の1の表 | 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」 |
|---|---|
| 別表第1の2の表 | 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」 |
| 別表第1の5の表 | 「特定活動」 |
これらの在留資格で在留する外国人を、過去2年間に、適正に雇用または管理をした実績があるなら、この要件に該当します。
「雇用」というのは何となく理解できますが、「管理」というのは具体的にどういうことでしょうか?
小澤:いい質問ですね。
ここで言う「管理」とは、「自社で直接雇用はしていないけど、外国人の管理をしている」場合を想定しています。
例えば、技能実習の監理団体は技能実習生の監理をします。でも監理団体が直接雇用するわけではない。雇用するのは実習実施者で、監理団体は監理者としてサポートする。こういう場合が「管理」にあてはまって要件イに該当することになります。
もっとも、個人事業主の場合は、この「管理」実績で申請するケースは少ないです。個人事業主の場合「雇用」実績で申請するケースが多いです。
「過去2年間」というのは何か理由があるのでしょうか?
小澤 登録支援機関に支援をおこなう体制があるかどうかを判断するための要件ですから、あまりに昔の実績だと心もとない、だから過去2年間という区切りをつけているんです。「10年前に外国人を雇用した実績があるけど、最近は実績が無い」だと、支援機関として大丈夫か?ってことになりますよね。
なるほど。「過去2年以内」というのは、いつから数えて2年以内なのでしょうか?
小澤 申請日を基準として過去2年以内です。
「過去2年以内」に雇用はしているけど、雇用していた期間が短い場合でも要件を満たすのでしょうか?
小澤 これも鋭い指摘です。実は、入管法施行規則第19条の21第3号には、「雇用の時期=過去2年以内」と規定されていますが、「雇用の期間(長短)」について規定はありません。
規定が無いということは、雇用の期間(長短)は審査基準にならないということです。
ということは、例えば過去2年間の間に、1日だけ雇用していた場合も実績として認められるのでしょうか?
小澤 理論的にはそうなります。
過去2年間の間の、どのタイミングで雇用したかについては、注意点はありますか?
小澤 雇用のタイミングについては「過去2年間」の期間内なら、どのタイミングでも可です。実際に、登録申請の直前に就労系在留資格の外国人を雇用して申請した案件で、登録された事例もあります。
そうなんですね。
小澤 でも、これには問題もあります。
先ほど言ったとおり「過去2年以内」というのは、登録支援機関に支援をおこなう体制があるかどうかを判断するために決められた要件です。
過去2年以内に1日間だけ外国人を雇用したことがある事業者に、支援をおこなう体制がある、と果たして言えるかどうか。この点は、今後改善が必要な点かもしれません。
確かに。
要件ロ 各種相談業務実績
小澤 次に、要件ロを見てみましょう。
ロ 登録支援機関になろうとする者が,過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
要件ロは、行政書士や弁護士を想定した要件です。「報酬を得る目的で業として」外国人に関する各種相談業務に従事した経験があるかが問われます。
行政書士や弁護士などの士業を想定しているので、他の業種の事業者が要件ロに該当するケースはあまりありません。
行政書士や弁護士であれば、誰でも登録支援機関になれるのでしょうか。
小澤 いいえ。行政書士や弁護士であるだけでは、登録支援機関にはなれません。
もう一度要件ロを見てみましょう。「外国人に関する各種相談業務に従事した経験」と規定されています。例えば、外国人の在留資格関連手続きを、報酬を得て取次ぎした行政書士などが、要件ロに該当します。
要件ハ 生活相談業務実績
要件ハは、どのような場合に該当するのでしょうか?
小澤 要件ハは、「生活相談業務実績」です。選任された支援責任者と支援担当者が、過去5年以内に2年以上、就労系の中長期在留者に対して業務として生活相談をおこなった経験があれば該当します。
要件イ「受入れ管理実績」や要件ロ「各種相談業務経験」に対して、この「生活相談業務実績」は該当する範囲が比較的広いと言えます。
例えば、技能実習の監理団体の職員として技能実習生の生活相談業務をおこなっていた者や、労働者派遣事業者の職員として技人国の外国人に生活相談業務をおこなっていた者を支援責任者・支援担当者に選任している場合などが該当します。
ここで重要なのは、「業務」としておこなっている必要があることです。ボランティアで生活相談をおこなった経験は該当しません。
技能実習の実習実施者の職員として、技能実習生のサポートをおこなっていた場合はどうでしょうか?
小澤 一概には言えませんが、該当する可能性はあります。以前当事務所で扱った案件で、技能実習の実習実施者の職員として、技能実習生に対して生活相談業務をおこなっていた人が、個人事業主として登録支援機関登録申請をしたケースでは、「生活相談業務実績」と認められて登録支援機関として登録されました。
要件ハ「生活相談業務実績」について、何か特徴などはありますか?
小澤 要件イ・要件ロが申請者自身に対して求められる要件なのに対して、要件ハは支援責任者・支援担当者に求められる要件であることが特徴です。
これが何を意味するかというと、申請者自身が要件イ~ハを満たしていなくても、要件ハに該当する人材を支援責任者・支援担当者として選任すれば、要件ハを満たすことになります。
なるほど。最近、登録支援機関として登録されるための基準が厳しくなってきていると聞きましたが、実際のところどうなのでしょうか?
小澤 確かに、登録支援機関登録申請をおこなった後、要件を満たすことの立証資料として、入管から追加資料の提出を求められるケースが増えています。
それから、2027年に育成就労制度が開始されますが、それに伴って登録支援機関の要件が厳格化・適正化されることが予定されています。ですので、現在では要件を満たす場合でも、将来満たさなくなる可能性があることに注意してください。
なるほど、今後は登録支援機関の要件が厳しくなるのですね。この点については、別の機会にお話しを伺わせて頂きます。
本日は個人事業主として登録支援機関になる場合について、行政書士の小澤先生にお話しを伺いました。
小澤先生、本日はありがとうございました。
小澤 ありがとうございました。