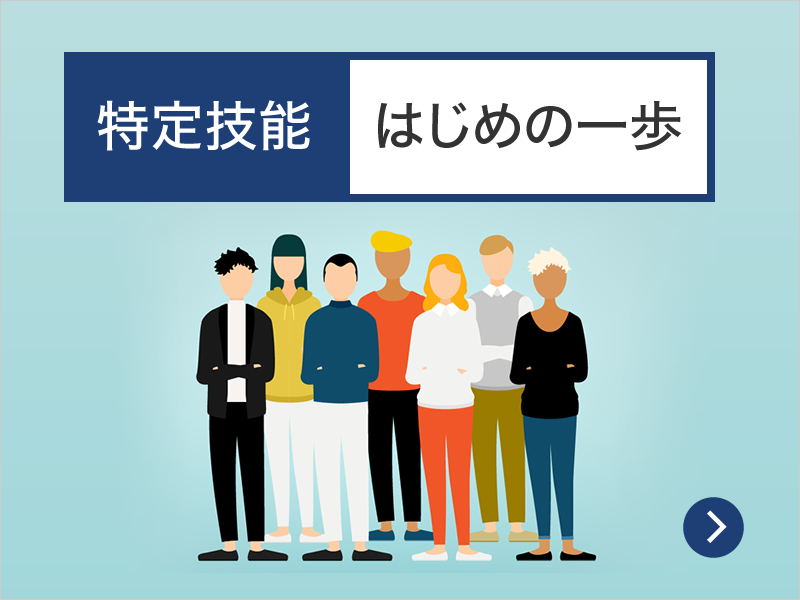外国人材を受け入れる制度として、「技能実習」と「特定技能」を活用してきた事業者さんも多いのではないでしょうか。
しかし今後は、技能実習ではなく「育成就労」という制度が開始されることとなります。
技能実習と育成就労は、共通する部分もあれば、大きく変更となる部分もあり、困惑している方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、育成就労制度に関して知っておきたい情報をわかりやすく紹介します。育成就労はいつから受入れ開始となるのかや、育成就労と特定技能の関係についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
育成就労とは
育成就労制度とは、日本で3年間、育成就労産業分野において就労することで「特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する」とともに、当該分野における「人材確保」を目的とした制度です。
これまでの技能実習制度は「日本の技術を母国に持ち帰り、発展に役立ててもらうこと」を目的としており、人手不足解消(人材確保)のために利用してはならないとされていました。
しかし育成就労制度は、人材確保も目的の一つとされています。
つまり育成就労制度では、外国人材は技能を身につけながら働き、将来的には「特定技能1号」として就労を継続することで、日本の人手不足解消にもつなげることを目指しているのです。
育成就労制度創設の背景
育成就労制度が創設された背景としては、現行の「技能実習生制度」に問題があったことが挙げられます。
そもそも技能実習制度は人材確保のために用いてはならないとされていましたが、現実的には国内の労働力不足解消のために利用されていたことも否めません。
また、日本の労働力不足も深刻で、技能実習生が経済社会の重要な担い手となっていることも事実です。日本の生産年齢人口は2040年までに1,200万人が減少するなど、労働力不足は今後も加速していくと考えられ、外国人材の活用は喫緊の課題といわれています。
しかし、外国人材を活用したいのは日本だけではありません。日本の近隣諸国・地域も外国人材を受け入れており、相対的に日本の魅力は薄れているのが現状です。
ここまで紹介した現状の課題をまとめると、次の2点が挙げられます。
- 技能実習制度の目的と実態が乖離している
- 日本の労働環境が外国人材にとって魅力的でない
これら課題を解決するために、技能実習に代わる新たな制度として「育成就労制度」が創設されることになりました。
技能実習制度と育成就労制度の細かな違いについては、後ほど詳しく紹介します。
特定技能に移行できる制度
「技能実習」で日本に来た外国人材も、「1号特定技能評価試験」に合格するなど一定の条件を満たせば「特定技能」へ移行することができます。(技能実習2号良好修了者であれば、移行時の「技能に係る試験」「日本語能力に係る試験」の合格条件が免除されます)
ただし、技能実習は必ずしも特定技能への移行を前提とした制度ではありません。そのため技能実習にある職種が、必ずしも特定技能と対応しているとは限らないのです。
一方、「育成就労」は特定技能に移行できる制度として整備されます。そのため育成就労産業分野は、特定技能と対応していることが特徴です。
なお、育成就労から特定技能1号への移行条件は、次の2つとされる方針が示されています。
- 技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)の合格
- 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)の合格
特定技能への移行要件を満たし、さらに在籍している受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えていれば、育成就労の途中で特定技能1号に移行することも可能となる見込みです。
また、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったとしても、最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針も示されています。
※技能実習は随時3級試験に合格すれば特定技能1号に移行でき、随時3級に不合格であっても評価調書を提出することで特定技能1号に移行可能です。一方で育成就労から特定技能1号になるには、(現時点の情報では)上記の試験合格が必須と見受けられます。この点だけ見ると、技能実習の方が特定技能1号への移行が容易ともいえるかもしれません。
悪質なブローカー対策も強化
育成就労の創設にあたっては、外国人材の保護も重視されてます。その一環として強化されるのが、悪質なブローカーの対策です。
転籍仲介状況を把握することや、不法就労助長罪の法定刑が引上げられることはもちろん、民間の職業紹介事業者の関与も当分のあいだ認めないことで、悪質なブローカーが徹底的に排除されます。
また、悪質な送出機関を排除するために、二国間取決め(協力覚書)を作成した国からの受入れのみが想定されていることもポイントです。
なお、特定技能にも二国間協定(MOC)は存在しますが、特定技能の場合は二国間協定を締結している国以外の国籍者でも受入れ可能です。
さらに、これまでは「監理団体」が技能実習生・受入れ企業をサポートしてきましたが、これが「監理支援機関」と名称変更され、許可制となります。監理支援機関が育成就労が適正に実施されているかどうか監理することで、制度の適正な運用を守っていく方針です。
これまで以上に安心して働ける環境を整えることで、日本で働きたいと思う外国人材が増えることが期待されます。
育成就労の受け入れ開始時期
「育成就労制度」と「改正後の特定技能制度」は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されるとされています。
2025年1月時点において厳密な施行日は未定ですが、令和9年(2027年)6月20日までに施行される予定です。
育成就労制度の対象職種
育成就労制度の対象職種(育成就労産業分野)は、特定技能の対象産業分野の中から一部が指定される見込みです。
具体的にはどの産業分野が指定されるかは、今後の省令で判明しますが、現時点では特定技能制度と同様になると考えられています。
育成就労では転籍も可能
育成就労制度の創設で注目すべきポイントの一つは、外国人材の「転籍」が可能となる条件が緩和されることです。
技能実習では、原則として転籍が認められません。(やむを得ない事情がある場合、2号から3号への移行は可能)
しかし育成就労では、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けることで、「本人意向の転籍」が可能となります。認定条件は次のとおりです。
- やむを得ない事情がある場合
- 同一業務区分内であり、就労期間(業務内容などを勘案して1年~2年の範囲で主務省令で規定)・技能などの水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)
受入れ機関(育成就労実施者)の要件
それでは受入れ機関(育成就労実施者)の要件についても見ていきましょう。
育成就労制度も、技能実習制度と同じく人材育成を目的としています。そのため受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制などの要件については、適正化して維持される予定です。
さらに、育成就労は人材確保を目的とし、特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく「受入れ対象分野別の協議会への加入」が要件に含まれるとされています。
なお、技能実習とは制度の目的が異なるため、育成就労においては帰国後の業務従事要件などの国際貢献に由来する条件は廃止される予定です。
外国人材側の要件
つづいて外国人材側の要件について見ていきましょう。
まず日本語能力に係る要件として、就労開始前に日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5など)の合格、もしくはこれに相当する認定日本語教育機関などによる日本語講習の受講が求められます。
ただし必要となる日本語能力レベルについては、育成就労産業分野によってはさらに高くなる可能性もあります。
なお、技能に係る要件はありません。
また、技能実習制度では家族の帯同は認められていませんが、育成就労についても家族の帯同は原則として認められません。
ちなみに、元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働く場合、条件が少し複雑になります。過去の技能実習期間は「育成就労期間」とみなされるため、2年以上の技能実習を行った外国人の場合、再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。
ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことが認められるとされています。詳細条件は今後の主務省令で定められるため、再来日の外国人材を受け入れる予定がある場合には情報収集しておきましょう。
育成就労と技能実習の違い 一覧表
それではここまで紹介してきたポイントをふまえ、育成就労と技能実習の違いについて一覧表で見てみましょう。
| 比較項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 目的 | 日本の技術を母国に持ち帰り、発展に役立ててもらうこと | 特定技能1号水準の技能を有する人材を育成すること
人材を確保すること |
| 技能水準 | 未熟練者 | 就労開始前に日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5など)の合格、もしくはこれに相当する認定日本語教育機関などによる日本語講習の受講
技能に係る要件はなし |
| 職種・分野 | 90職種
特定技能産業分野に設定が無い職種が一部有(2025年2月時点) |
16分野
特定技能産業分野と一致 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年(試験不合格の救済措置を利用した場合は最長4年) |
| 期間終了後 | 原則として帰国
(条件を満たせば特定技能へ移行) |
試験合格後に特定技能へ移行 |
| 転籍 | 原則として不可 | 条件を満たせば本人意向の転籍も可能 |
| 派遣 | 不可 | 農業漁業では可能 |
| 日本語能力 | 就労開始時の条件は原則なし
(介護は日本語能力試験N4など) |
日本語能力試験N5など
(原則) |
| 監督機関 | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構 |
| 監理団体 | 監理団体
(受入れ企業との関係が密接になりすぎ、監理が不十分な場合もある) |
監理支援機関
(外部監査人の設置が義務化され、独立性・中立性が確保) |
| 途中での特定技能1号への移行 | 原則不可
(やむを得ない事情による転籍の場合は「特定活動」への変更が可能な場合有り) |
一定条件、期間を満たせば可 |
| 転職(同一の在留資格内) | 原則不可 | ・やむを得ない事情による転籍可
・その他一定条件、期間を満たせば可 |
| 試験不合格の場合の救済措置 | 評価調書を提出することで特定技能1号に移行可能 | 最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針が示されている |
| 家族帯同 | 原則不可 | 原則不可 |
現行制度で在留する技能実習生の移行について
さて、育成就労制度は令和9年(2027年)からスタートする予定ですが、現行制度で在留する技能実習生は、育成就労に移行していくことが可能なのでしょうか。少し複雑ですが、いくつかのケースを例に解説します。
まず、育成就労制度の施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合です。この場合は施行日後に技能実習を行うことが可能で、要件を満たせば次の段階の技能実習まで引き続き実施できます。
そして施行日時点で技能実習1号で在留している方は、技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号への移行が可能です。一方、施行日時点で技能実習2号で在留する方が、技能実習3号へ移行する場合、範囲が限られるため注意しなければなりません。
次に施行日前に技能実習計画の認定を申請している場合です。この場合、施行日以後に技能実習生として入国できる可能性があります。ただし認定された技能実習計画が、施行日から3か月以内に開始する内容である場合に限ります。(技能実習計画が施行日以後に認定される場合もあります)
ここまでが、施行日後も技能実習を実施できるケースです。なお、これらのケースに当てはまる場合、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません。
つづいて施行日後に技能実習を実施できない例を紹介します。たとえば施行日前に技能実習を終えて、すでに出国している場合は、技能実習生として再度入国することはできません。(ただし技能実習を行っていた期間や職種によっては、育成就労外国人として再度入国することができる場合もあります)
令和9年(2027年)の施行日をまたいて技能実習を実施する予定がある事業者さんは、今後の追加情報にも注意しておくといいかもしれません。
まとめ
育成就労制度は、技能実習とは異なり「人材確保」を目的としており、特定技能へも移行しやすいことが特徴です。
育成就労で3年、特定技能1号で最大5年、計8年働いてもらえれば、人手不足解消効果も大きいでしょう。
ただし、育成就労の施行は令和9年(2027年)からで、まで詳細が決まっていない事項もあります。今後発表される情報を集めながら、少しずつ準備を始めてみてください。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)